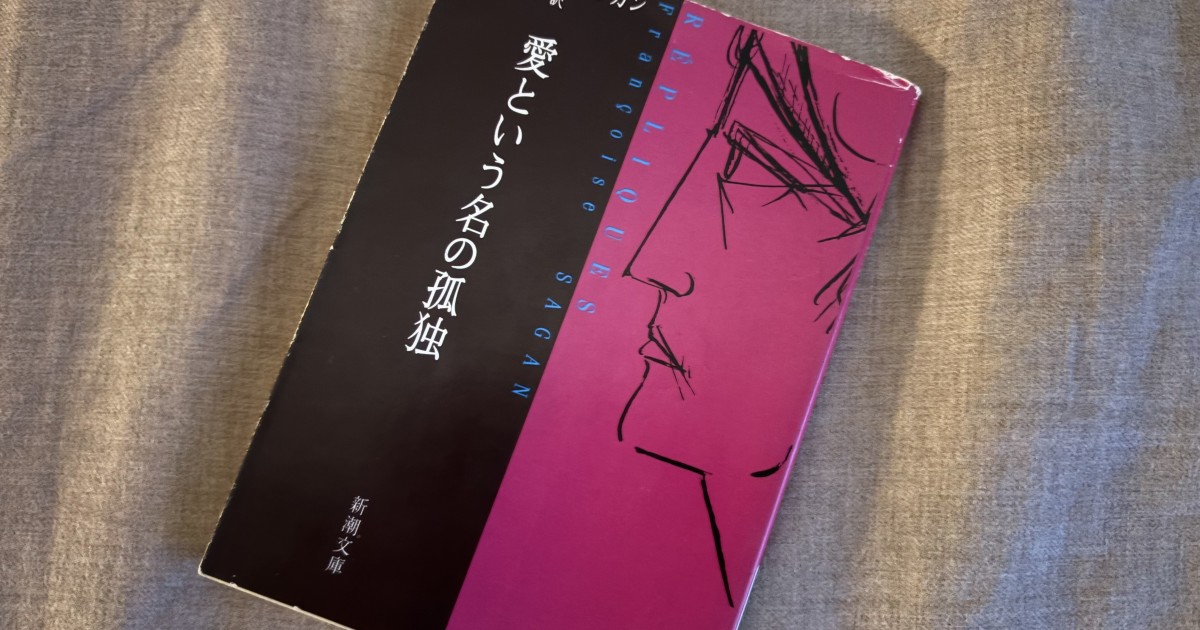『Lover』(1月24日)
朝、母に電話した。ゴホゴホッとほとんど話ができないほど、母の咳がつづく。いまから行くね、と思わず見兼ねて言ってしまった。今日は夕方までひとり原稿をやろうとしていたので、問題はなかった。
また、スープストックと草団子、のど飴などなどを買ってから、東横線に乗った。
車内は混んでいて、今日が土曜日だと思い出す。昨日、『BEFORE DAWN』だったのだから、今日は土曜日で間違いない。わかっているつもりなのに、どうしても曜日感覚が狂ってくる。
番組内で、昨日はこのレターのエッセイ『底なしの出会い 01』を朗読した。
実家のマンションの部屋の前まで着き、インターフォンを押すと「カギ開いてるわよー」と母の声。相手がピッキング犯だったらどうするんだ! と母に注意しながら、買ってきたものを渡す。「だいたいあなたが帰ってくる時間を計算して、ドアの鍵を開けているから大丈夫よ」と、全然大丈夫じゃない解説をする母。
一見、母の顔色はいい。
父が台所でりんごを剥いていた。母の咳はおさまっている。「昨日、お母さん、咳で寝れなくて大変だったんだ」と言いながら、父は、りんごが盛られた皿をテーブルの上に置いた。「ちょっと酷かったときがあっただけよ」と母が強がる。
「それが二時過ぎくらいだ。で、ふたりでもう起きて、お前の番組を聴いてたんだ」と父が言った。まるで怒っているかのような言い方、表情だったが、これがこの人の普通なのだ、と最近やっと理解できるようになってきた(遅い)。
「今日のラジオで最初にかかった曲、あれどなた? いい曲ね。あとあなたの文章よかったわ。いい仕事ね」母は隅々まで褒めてくれた。「よくやってる」父もひと言、そう言ってくれた。
あの曲は、君島大空の『Lover』だ。
「週刊新潮、お父さんのこと書いてあって、笑っちゃったわ」と母は白湯をすすりながら言った。そのあと、すぐにゴホゴホッと咳が止まらなくなったが、それでも笑ってくれた。
今週の週刊新潮は、実家のことを書いた。
久々に実家に戻ったら、父が不機嫌で、その理由が父が大好きなテレビが映らなくなったことだった、ということを書いた。配線を確認しても映らない。父はどんどん不機嫌になる。大谷の試合がその時間行われていて、それが観れないことが父は許せない。ふと、テレビの横の「電源」というボタンを見つけ、「これ押した?」と訊いてみた。「なにもしてない!」とほぼキレながら父が言う。まあ、とりあえず、くらいの感じで押してみると、画面に大谷が大映しになった。
なんてことはない。電源、を間違って押してしまって、テレビがつかなかっただけだった。「なんだ、そんなボタン押してないぞ!」父はまだ怒りを収めない。が、大谷が映っている事実に、口元が緩み始め、ついにはニヤニヤしてしまう。ああ実家だ。またしても実家としか言えない出来事だった。
そんな話を書いた。「あれ、全部ほんとのことねえ」ゴホゴホッとまだ咳き込みながら、母は口を抑えて笑っていた。父は自分で剥いたりんごを食べながら、ただただムスッとしていた。

父はムスッとしながらも、みかんまで剥いてくれた。悪い人ではない
母が咳で眠れず、夜起きたときに、ちょうど自分のラジオ番組がO.A.されていてよかった。四年とちょっと担当させてもらっていたからこそ、それが起きた。母が咳き込みながらも、笑ってくれた週刊新潮の『それでも日々はつづくから』は今週で第245回を迎えた。連載はもうすぐ四年を迎える。ここまで粘ってきてよかった。本当によかった。