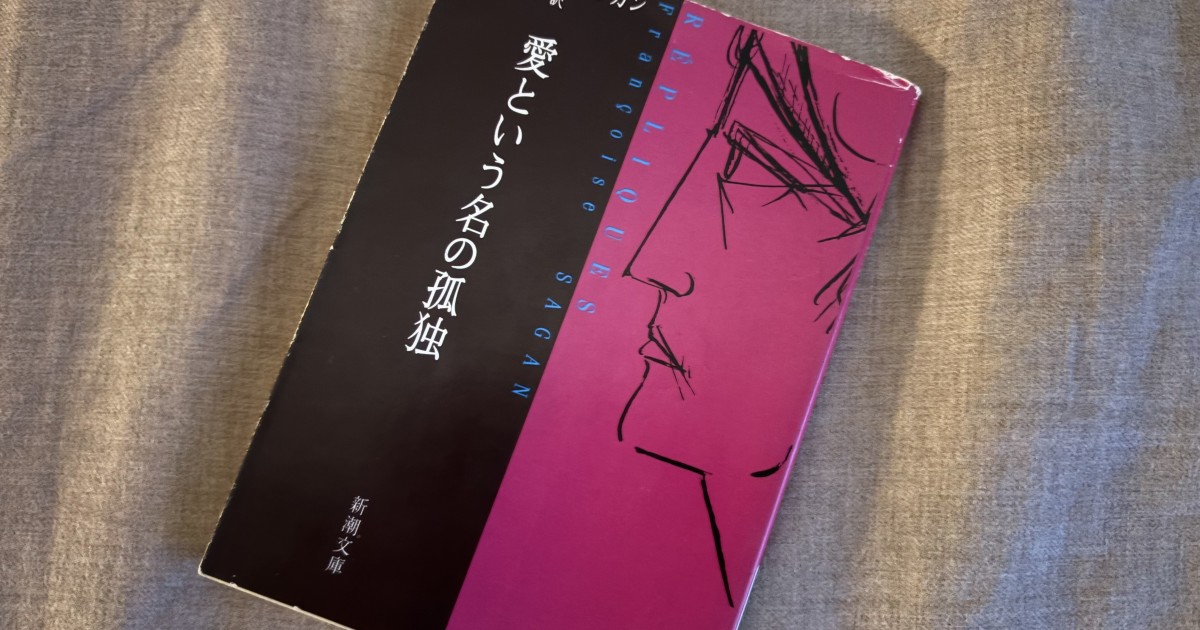九年間の習慣(底なしの出会い)
通夜が無事に終わったあと、そのまま葬儀場に、父と妹と僕の三人で泊まった。僕たちの泊まった部屋には、『遺族控室』のプレート。隣は、母の微笑んだ遺影が飾られた祭壇の会場。午後十一時には布団を敷き、父を真ん中にして、川の字で寝た。
程なくして父と妹、両方のいびきが聞こえてくる。フンゴー、フンゴー。同じ周波数のいびき。やっぱり家族なんだなあ、と思う。それからどのくらい経っただろう、ふと目が覚めて、隣を見ると、父の姿がない。抜き足差し足、光が漏れるほうに進んでみる。
父は祭壇が飾ってある会場の一番前に座っていた。両足を投げ出し、両手を頭の後ろで組んで、ボーッと祭壇に飾られている母の遺影を眺めていた。言葉を使わず、なにか会話をしているように見えた。僕はその光景を見て、抜き足差し足、また『遺族控室』に戻った。「フンゴー、フンゴー」妹のいびきは朝までつづいた。父は朝まで戻ってこなかった。
100%僕が悪い理由で、母が高校に呼び出されたことがあった。放課後の教室に机を並べて、母と僕は並んで座らされる。前には担任が、カンカンに怒りながら座っていた。母は何度も何度も頭を下げる。僕はもう消えたくなるほど、いたたまれない気持ちになっていたのを憶えている。
帰りの電車の中で、母の提案で、ラーメンを食べて帰ろうということになった。ラーメンをすすりながら、母のほうも見ずに、「すみませんでした」と僕は謝る。ズズズ……、と母はしばらくラーメンをすすりながら、なにも言わない。それからゆっくり、「いいのよ。家族は順番に迷惑をかけて」とだけ言った。
妹のいびき声がずっと聞こえている、父不在の『遺族控室』の布団の中で、僕はあのときの母の言葉を思い出していた。
遺族控室はかなり乾燥していて、起きると喉が少々痛かった。妹も、もう起きてはいたが、布団の中で丸くなって「喉が痛いよ〜」と訴えていた。「お茶でも買ってこようか?」と提案すると、「温かいやつ」と妹が言ったあと、「お父さんのもね」と付け加えた。
僕は簡単に支度を済ませ、葬儀場の近くにあるコンビニまで行く。ホットの焙じ茶を三つと、あんまんを三つ。ビニール袋に入れてもらって戻ろうとしたとき、左手で持っていたスマートフォンを操作して、ふと母に電話をかけてしまった。
母が、がんの手術をしてから、毎朝ほぼ必ず、最寄りの駅に向かう途中に電話をかけていた。筋トレをやっている人が、一日サボると気持ち悪くなるのと一緒で、かけないほうがしっくりこない程、電話をかけるということは習慣化していた。かけてしまった途端、あっ、と気づいてすぐに止めた。