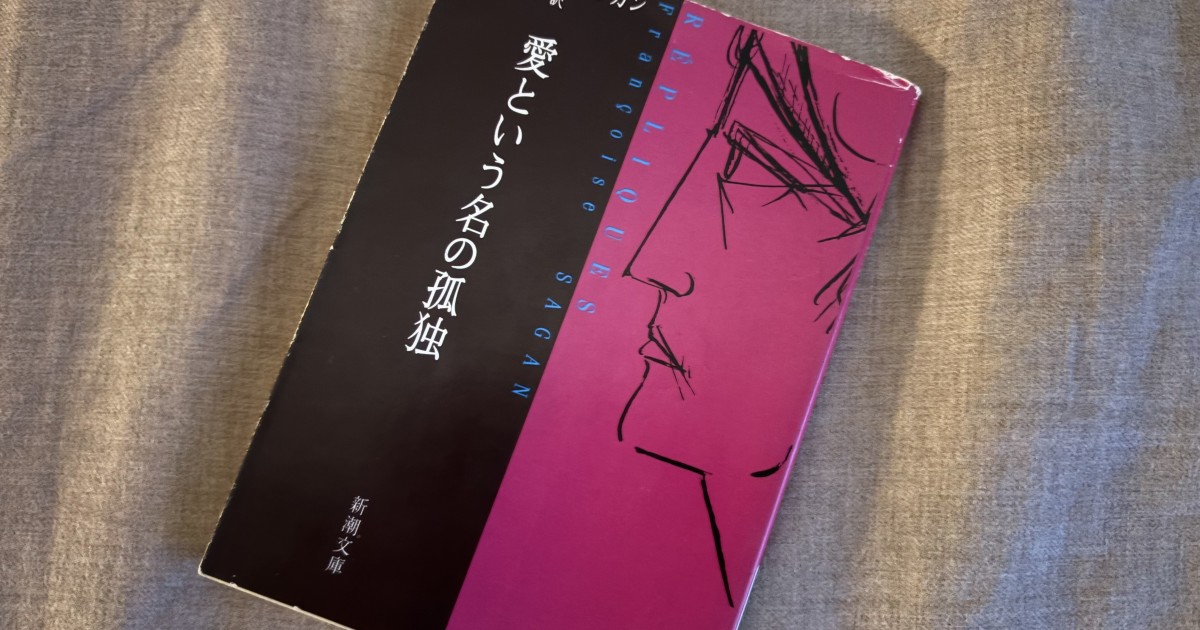「暖かくしなさい」底なしの出会い#06

僕は毎朝、仕事場に向かう道すがら、母に電話をかけることにしている。今朝、電話口の母が、ゴホゴホと咳き込んでいて心配になった。
母は僕が接してきた人の中で、間違いなく誰よりも怖がりなので、毎回電話の最後には、今生の別れのようなことを言い出す。気持ちはわかる。わかるがこちらは明日も電話をかけると決めているし、母は明日も電話に出てくれると信じている。だからあえて湿っぽくしないようにして電話を切る。
今日も最後のほうには、生前贈与の話、癌の治療でお金をたくさん使ってしまった話などをずっとしていた。
九年前、母が初めて癌の手術をしたとき、とんでもない量の内臓を除去し、その実物を家族は見せられた。仕事があって、遅れて到着した僕に、父は、「もうお母さんと話せなくなるかもしれないんだぞ!」と激怒した。
父も余裕がなかったんだと思うが、あのときは本当にいろいろと仕方がなかった。季節は冬。病院の窓がカタカタと北風が当たってずっと音を出している。母は酸素マスクをして、静かにベッドに横たわっていた。聞いたこともない機械音がずっと鳴っていた。
僕たち家族は、母を取り囲むようにベッドの周りで見守っている。僕は布団の中に自分の手を入れ、母の手を静かに握ってみた。母の手は、外気にずっと当たっていたかのように芯から冷たい。僕はその手を強く握る。しばらくすると、母はフッと目を開け、僕を見つめた。うつろな目。カタカタとずっと風の音。
噛み締めるくらいゆっくりと母は言う。「今日は寒いでしょう。暖かくしなさい」と。それを聞いて、僕は初めて涙が止まらなくなった。母が、次の瞬間には消えてしまうような気がした。それほどに、母の命の灯火は弱く、ゆらゆらと不確かに風に揺れていた。
でもそこから様々な治療を乗り越え、母は生きてくれた。あの夜のことを考えれば、いま、毎日電話をして、「今日の大谷翔平」の話から、近所のどーでもいい出来事まで話し合える時間すべてが、間違いなく奇跡だ。怖がりの母が、自分の身体の中に巣食うがん細胞に怯える気持ちはよくわかる。わかるが、この九年間の奇跡にもぜひ目を向けてほしい、そう思っている。
僕は次の瞬間に、どうなるかわからない仕事に就いている。「不安でしょう?」と母はもとより、友人たちにも顔を合わせるたびに言われる。母譲りの怖がりなので、正直不安で不安で仕方がない夜もある。ままある。睡眠薬を飲んでも眠れずに、明け方までソファでただただボーッとしていることもしばしば。